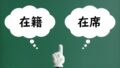「さばく」には「裁く」「捌く」の2つの漢字がありますが、意味はずいぶんと違うので、それぞれの意味を理解した上で、論文・小論文では使うようにしていきましょう。ここでは、「裁く」「捌く」のそれぞれの意味の違いや例文について解説していきます。
「裁く」と「捌く」の違い
裁く(さばく)
意味:判断を下すこと。
「裁く」は、善悪・理非についての判断を下すという意味です。とくに裁判官が事件について判断を下すときに用います。
捌く(さばく)
意味: 手際よく処理すること。
「捌く」は「裾を捌く」など入り乱れたり絡んだりしたものを解きほぐす、「魚を捌く」など鳥や魚などの生き物を解体する、「手綱を捌く」など扱いにくいものをうまく扱ったり道具などを使いこなしたりする、「仕事を捌く」などものごとを手際よく片付ける、「在庫を捌く」など商品を売りつくすなど広く使われます。常用外漢字なのでひらがなで書くこともあります。
ハラスメントをさばくは裁くが正しい
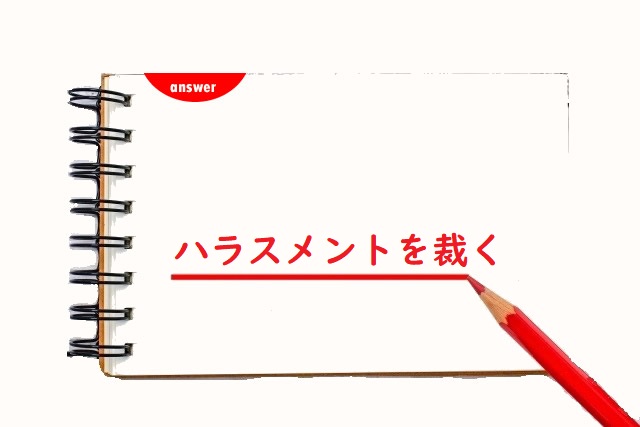
「ハラスメントをさばく」はハラスメントの理非について判断を下すことなので、ここでは「裁く」が正解です。
「裁く」の例文
例文1:裁判官は犯罪者の罪を正しく裁く仕事です。
「罪をさばく」は罪の善悪について判断を下すことなので、ここでは「裁く」を使います。
例文2:悪事を犯せば法の裁きを受けなくても、罪悪感は残るだろう。
「法のさばき」は法律で罪の善悪に判断を下すということなので、ここでは「裁く」を使います。
「捌く」の例文
例文1:釣った魚をその場で捌いて食べる。
「魚をさばいて食べる」は魚を解体することなので、ここでは「捌く」を使います。
例文2:Aさんは手際よくいろんな人に仕事を捌くので、彼に任せると物事がスムーズに進む。
「仕事をさばく」は仕事を手際よく片付けることなので、ここでは「捌く」を使います。
論文・小論文で「裁く」と「捌く」を使い分ける視点
「裁く」は理非の判断を下すこと、「捌く」は手際よく処理することを意味します。論文・小論文ではそれぞれ意味が違うので区別して使うようにしましょう。